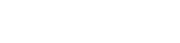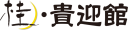「概念コーデ」で推しを表現しよう
皆様こんにちは。貴迎館の武下です。
振袖を選ぶ時、そこには必ず大事にしたいテーマがあるものです。一生に一度の舞台を華々しく飾るのか、着用される方の魅力を引き出すのか、他の誰とも違う独自の路線を行くか……色や柄、あるいは小物一つでも雰囲気が大きく変わるからこそ、吟味に吟味を重ねますよね。ゆえに、コーデの方向性は何よりも重要となってきます。
そこで注目したいのが、「概念コーデ」と呼ばれる考え方です。近年のファッショントレンドにおいて度々取り上げられており、新しく生まれた言葉ながら爆発的にその認知度を高めています。今回はその「概念コーデ」について、そもそもの意味や詳しい内容、さらには振袖への応用例などを解説いたします。
1.概念コーデとは何か?

「概念コーデ」とは、単なる“キャラクターなりきり”や“コスプレ”とは異なり、特定の作品・キャラクター・世界観・テーマ・イメージ(色、ムード、モチーフなど)を、日常服・ファッションアイテムを通して「象徴的に表現する」スタイルです。つまり、完全な仮装ではなく、「あくまでファッションとして成立させたうえで、そこに“概念(=作品・テーマ・物語性など)”を込める」ことを目指すものです。
具体的には、以下のような特徴を持つことが多いでしょう。
- キャラクターそのものを完全に再現するのではない。そのキャラクターの「印象色」「モチーフ(例:バラ、骨、炎、羽根など)」「性格性質」「物語上の象徴」などを抽象化して取り入れる
- 日常性・現実性を保つ。極端な武器や過剰パーツを排除し、着回し可能な服・アイテムで「それっぽさ」を出す。
- 視覚的ヒント(キーアイテム、小物、配色)を用いる。一見してわかるかどうかよりも、気づいた人がニヤリとする程度の“隠し味”や“象徴性”を宿すことを重視する。
・バランス、シルエット、素材感、テクスチャー、色の調整など、ファッションとして見ても成立するようにデザインされている。
このように、概念コーデは「ファッション × 物語性/世界観表現」のハイブリッド領域で、「ただの仮装ではない芸術性」や「着る人のセンス」が問われる表現形式です。
2.どんな文脈で生まれたのか

/概念コーデを語るうえで避けて通れないのが「コスプレ」の存在です。コスプレは、アニメ・漫画・ゲーム・映画などのキャラクターを可能な限り忠実に再現する仮装芸術です。ウィッグ、プロップ(武器、小道具)、アイメイク、架空装備などを駆使し、そのキャラクターになりきることが目的です。
しかし、コスプレの「完全再現性」「徹底した装飾性」は日常生活には馴染みにくく、コストや可動性、視認性などの制限も伴います。そうした制約のなかで、コスプレ的な発想(キャラクターや作品世界への愛着・再現願望)を「日常にも持ち込みたい」という欲求から、より“薄められた”表現として進化してきたのが、「概念コーデ」の萌芽であると考えることができます。
実際、近年のSNS(特にInstagram、X、TikTok など)において、コスプレとは異なるスタイルで「作品イメージを服で表す」投稿が目立つようになってきました。服飾系ブランドや個人クリエイターが、映画・絵画・古典芸術・アニメなどをモチーフにしたコーデを「概念コーデ」として発信するケースも増えています。たとえば、アパレル企業「ズーティー/イーザッカマニア」では、映画をテーマに1日ずつコーデを仕立てる特集を展開しており、これ自体が “概念コーデ”の文脈を普及するきっかけになっています。
このように、コスプレ文化からの“脱皮”として、よりゆるく、よりファッション寄りに、かつ物語性を持たせられる表現が概念コーデという位置を得たわけです。
もう一つの歴史的文脈は、日本のストリートファッション文化、特に原宿・裏原系、ロリータ、ゴシック、ヴィジュアル系、モード系などとの接点です。これらのファッションジャンルは、既存の服飾規範からの逸脱、自己表現性、独自美学の追求という性格を持っており、そこには「服を通して世界観を語る」精神がすでに根付いていました。
概念コーデはこの流れを、さらに「物語性」や「象徴主義」に引き寄せたもの、と言えます。つまり、ストリート・モード系で培われた「見た目の破綻性・インパクト性」「意匠遊びを楽しむ自由性」を、物語演出という新たな要素で拡張したのが概念コーデと呼ばれる表現なのです。
さらに背景の一つとして、SNS/写真文化の発展があります。かつてはファッション誌が美意識を牽引していましたが、スマートフォン・Instagram・TikTok の普及により、誰もが視覚表現を発信できる時代となりました。その結果、「映える」「いいねを稼ぐ」「一目で引きつけるビジュアル性」が重視されるようになり、服装においても「ストーリー性」や「世界観」を可視化するニーズが強まりました。この社会技術的変化も、概念コーデを流行らせている一因といえます。
3.コスプレとの違い

先にも述べたように、概念コーデとコスプレは似て非なる存在です。その違いについて整理し、境界線や共通点を列挙します。
再現性 vs 抽象性
- コスプレ:元となるキャラクター・作品を忠実に再現することが目標。ウィッグ・メイク・プロップ・特殊装飾などを駆使し、「このキャラクターだ」と即判別できる水準を目指します。
- 概念コーデ:完全再現を目指すのではなく、そのキャラクター・世界観・雰囲気・テーマを象徴的に落とし込んでいます。あえてグレーな部分を残し、想像できる余地を残すのも特徴です。
非日常性 vs 日常適用性
- コスプレ:非日常シーン(イベント、撮影会、ステージなど)で着用されます。普段街を歩くには過剰で扱いづらいデザインが多いです。
- 概念コーデ:普段着や日常着として着ることを意識されるケースが多い。日中の買い物、カフェ、展示会へ行くなどの場面でも馴染むよう、ほどよく抽象化・抑制されます。
見える/見えない“ヒント”の活用
- コスプレ:そのままキャラクターを再構築するため、「特定の何かをつけていないとキャラだと認識されない」パーツが多く含まれます。
- 概念コーデ:見えない/わからない部分を残しつつ、気づいた人がニヤっとする要素(配色、小物、柄、デザインの象徴性)を仕込むことがむしろ美徳となることがあります。
変身 vs 投影
- コスプレ:キャラクターへの変身が主軸です。
- 概念コーデ:着る人自身の個性や体格・嗜好を残しながら、そこに「物語性を投影」することが重視されます。
もちろん、概念コーデとコスプレは完全に分断されているわけではありません。むしろ両者が重なりあうグラデーションが存在します。
たとえば、軽めのコスプレ衣装を、あえて日常服とミックスして“概念コーデ風”に着こなす人や、コスプレ衣装を意識的に崩して日常性を加える人もいます。また、「キャラクターが持っているアイテム(例:杖、武器、シンボルアクセサリー)」を控えめに取り入れることで、仮装感を抑えつつ概念表現を狙う手法などもあります。
結論として、コスプレと概念コーデは目的・方法・着用文脈の点で異なるものですが、その間には自由な重なりと移行が許されていると言えます。
4.落とし込みの具体例
ここでは、実際にSNSやメディアで話題になった概念コーデの例を見ながら、どのように構成されているか分析を加えていきます。
1.ちいかわ×地雷系
コスプレイヤーの高嶺ヒナさんが「ちいかわ」の登場キャラクターであるモモンガを意識した地雷系(フリルやブーツなどロリータ要素の強い系統)の概念コーデを披露した例があります。袖口とスカート裾のファーやモノトーンのカラーリングなどファッションジャンルとキャラクターらしさを融合させた表現であり、どちらの要素も損なわずに一つのファッションとして高いレベルで成立させている例と言えます。
2.銀河鉄道999×冬服
続いては、モデルのmimosaさんによる概念コーデです。「銀河鉄道999」の登場キャラクターであるメーテルをモチーフにしており、トレードマークの黒い帽子を筆頭にキャラクターの要素をふんだんに取り入れています。一方で組み込まれているアイテム自体はいずれも日常生活において違和感なく着用できるものであり、コスプレ感を打ち消しつつメーテルを連想させられることも特徴です。
3.呪術廻戦×着物
洋服はもちろん和服で概念コーデを仕上げている方もいます。フォトグラファーのさんかくさんは、「呪術廻戦」の登場キャラクターである五条悟を着物で表現しました。
- オレンジの半襦袢(キャラクターの印象色を反映)
- 黒の透け感のある絽の着物
- 帯に「六眼」をモチーフとした模様を選ぶ
- 帯締め・帯揚げの配色(紫/青/赤など)でキャラクターの術式・眼のイメージを暗示
- 小物(サングラスなど)をアクセントに使う
という手法を取っています。着物という衣装の枠内で、要素を絞りつつキャラクター性を印象付けているのがポイントです。このように、印象色 + モチーフ + アクセントを掛け合わせることで、完全な仮装とは異なる“概念の再現”が成立しているわけです。
5.振袖と「推し」の融合
推し活が一般的な文化として定着した今、「推しを応援する」は日常の一部。そして、その愛を表現する手段として急速に注目されているのが「推し概念コーデ」です。とりわけ、人生に一度の晴れ舞台である「成人式」に身につける振袖で、推しへの想いを形にする女性たちが増えています。「振袖で推し活?」と驚かれた方もいらっしゃることかと思います。ですが、振袖の原義から決して外れたものではありません。
振袖とは未婚女性の第一礼装にして日本文化の象徴的なファッションアイテムです。その瞬間の自分を表現する象徴とも言えます。そこに人生を豊かにしてくれた「推し」への愛情を込めるのは、極めて自然な流れなのです。
推しの存在が自分のアイデンティティの一部になっているならば、「推しを感じさせる色」「推しの物語を連想させる柄」「推しのキャラクター性を反映した小物選び」は、自分自身を語る最高のコーディネートになります。
6.コーデ組み立てのコツ

とはいえ、いきなり概念コーデに挑むのは少々ハードルが高いのもまた事実です。そこで、具体的にどのような段取りを組むとよいかかいつまんで説明いたします。
1.対象設定とコンセプト抽出
まず行うべきは、「どの作品/キャラクター/テーマを扱うか」を決定することです。そして、そこから「このコーデで表現したい印象・要素」をできるだけ明文化します。紙に書き出すことで、意図を明確にするという効果があるのです。
2.要素の優先順位付け
すべての要素を服で再現することは難しいので、どの要素を「必ず入れるか」「サブで入れるか」「省くか」を決める必要があります。優先順位をつけずにあれこれ盛ると、結果的にごちゃごちゃした印象になりかねません。
たとえば、「印象色」「モチーフ・シルエット」「アクセント小物」の三段階に分けて、“メイン要素 × サポート要素 × アクセント要素” というように分ける設計が有効です。
3.アイテム選び、テクスチャー計画
次に、具体的なアイテムの選定です。ここでは次のような点に注意するとよいでしょう。
- 振袖の色や素材感がコンセプトに即しているか
- 裏地やパーツの素材でニュアンスを出せるか
- 刺繍や柄でモチーフを象徴的に落とし込めないか
- 小物で要素を補填できないか
4.試着・修正・ブラッシュアップ
実際に着用して鏡に映してみると、「思ったよりモチーフが目立たない」「印象色が浮きすぎる」「動くとバランスが狂う」などの課題が出てくることがあります。試着を重ねて小物配置を変えたり、色味を調整したり、構成を見直すなどの試行錯誤を必ず行いましょう。
7.推し振袖や概念コーデも桂におまかせ

きものサロン桂では、お客様一人ひとりの想いに寄り添ったコーディネート提案を行っています。
・豊富な色や柄バリエーション
→ 伝統的な古典柄から、トレンド感のあるモダン柄まで、推しのイメージに合ったデザインがきっと見つかります。
・小物のセレクトも自由自在
→ 帯締め・帯揚げ・重ね衿・草履・髪飾りなど、カスタマイズ可能。パールやレース、リボンなどの“推し感”小物も豊富に取り揃えています。
・前撮りも成人式当日も安心サポート
→ フォトスタジオ併設。推し活を感じさせる特別なカットや小道具の持ち込みにも柔軟に対応。世界に一枚の記念写真が撮影可能です。

きものサロン桂 貴迎館
〒760-0079 高松市松縄町1067-19
TEL 087-869-2255 営業時間 10:00~19:00
きものサロン桂 丸亀店
〒763-0055 丸亀市新田町150ゆめタウン1F
TEL 0877-58-2255 営業時間 10:00~19:00