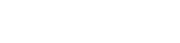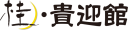大正浪漫前撮りスポット~丸亀編~
皆様こんにちは。貴迎館の武下です。
今回ご紹介する前撮りスポットは、香川県丸亀市に位置する 中津万象園・丸亀美術館 です。庭園としての風雅さと、展示施設としての文化性を併存させる複合的な観光スポットとして知られています。園部分は大名庭園として築かれ、池泉回遊式の構成を持ち、自然と調和した景観演出がなされています。一方、敷地内に併設された美術館(絵画館・陶器館)では、西洋絵画や古代から中世の陶磁器・装飾品などが展示されており、文化的な深みを感じられる場ともなっています。今回はこの庭園について、歴史や特徴、現代における役割などを解説してまいります。

中津万象園は、香川県丸亀市中津町に所在する池泉回遊式の大名庭園で、邸内には 丸亀美術館 が併設されています。元は丸亀藩主・京極家の別邸庭園として 1688年(貞享5年)に築庭されたもので、総面積は約15,000坪(おおよそ50,000㎡)とされ、京都や近隣名園と比しても決して小さくない規模を有しています。庭園名「万象(ばんしょう)」とは、「森羅万象」「宇宙に存在するすべてのもの」を意味し、自然・空間・人工が調和する場を志した命名と伝えられています。現在は、市民や観光客が訪れる文化レガシーの拠点であり、庭園としてだけでなく美術館、イベント空間、結婚写真ロケーションや伝統文化発信の場としても機能しています。

建設の背景と意図
中津万象園は、1688年(貞享5年)に丸亀藩二代目藩主 京極高豊(きょうごく たかとよ) によって築庭されたと伝えられています。
当時、丸亀城下に近接しながらも海浜(中津の浜)に近い場所を選び、海の景色や潮風を取り込む設計を意図した「汐入(しおいり)」式の要素も感じさせる様式が取り入れられています。
さらに、京極家の旧領である近江(滋賀県)を思い、「近江八景」の風景を模した島々を池に浮かべ、橋で繋ぐ趣向を採るなど、郷愁と趣を兼ねた造形が意図されました。
池の中心となる「八景池」は琵琶湖を模したと言われ、そこに「晴嵐」「帆」「雁」「雪」「雨」「鐘」「月」「夕映」などの名を付けた島々を配し、それぞれ趣の異なる橋を架ける設計がなされています。
このような設計は、江戸中期以降の大名庭園で見る「回遊式庭園」の典型的要素を備えつつも、海と水際を取り込むユニークな要素も併せ持つ構成です。
江戸後期〜明治期:変遷と所有変化
大名庭園であったゆえに、明治維新以降の藩制度解体の波を受け、所有や運営形態に変遷がありました。詳細な中間期の記録は限定的ですが、20世紀以降には民間の関与や保存活動が徐々に始まります。特に、荒廃や管理放棄の時期も経験しており、過去には園地が荒れたり建造物が損壊したりする時期もありました。その後、地元有志・保勝会(庭園を守る組織)が関与し、保存・修復活動が進められてきた歴史があります。
現代への復興と整備
近年では、中津万象園を未来に残すための支援・寄付の制度が整備され、公財団法人「中津万象園保勝会」が設立されて活動を行っています。また、丸亀城天守との共通入園券を設定するなど、地域観光との連携を強める取り組みも行われています。
こうして、藩主別邸庭園としての発祥から、近代を経て荒廃と復興を繰り返し、地元と観光資源としての価値を見出されて今に至るという歴史的経路をたどっています。

池泉回遊式構造と島・橋の配置
中津万象園は、典型的な 池泉回遊式庭園 の構成を基本としています。すなわち、中心に大きな池(八景池)を配置し、その周囲・池面に複数の島を設け、それらを橋で結びながら回遊できるようにする構成です。
島にはそれぞれ「雁行島」「晴嵐島」「月島」「夕映島」など、近江八景の名を冠したものがあるとされ、それぞれ異なる風情を持たせています。
複数の橋が、それぞれ違った形式で島を結び、庭路体験に変化を与えています。なかでも特筆されるのが 邀月橋(ようげつばし) で、長さ約30m、朱塗りの大橋で、島と島を結ぶのではなく池を跨ぐ形になっています。
この邀月橋という命名には「月を招く」という意味が込められ、橋上で月影を愛でる趣向が意図されたと伝わります。
また、他にも太鼓橋形式の観月橋、水蓮橋、臥雲橋など趣の異なる橋が点在し、視線と歩行の変化を楽しませます。こうした構成により、「水辺・空・緑・橋梁」が相互に呼応し、回遊することで次々に異なる景観が展開するよう設計されています。
樹木・松林と名松「大傘松(千代の傘松)」
庭園内には 1,500本以上の松が植えられており、その緑が庭全体の基調色となっています。特に有名なのが 大傘松(千代の傘松) で、直径15メートルに及ぶ伞型(かさがた)に剪定された一本の松で、推定樹齢 600年以上とも言われ、「日本の名松百選」にも選ばれています。この大傘松の剪定や維持管理には、年間で多くの庭師・技術者が関わっており、高い技術を要する作業です。
さらに、三笠宮崇仁殿下が植樹されたゴヨウマツや、扇松(おうぎまつ)など、京極家ゆかりの松も点在しています。その他、庭域には季節の花木・低木・草本類も植栽され、四季折々に庭の風情を豊かに彩ります。
建築・茶室・社・見所構造物
庭園内・周辺には、景観構成を補強する建築物や茶室・社などが配置されています。
観潮楼(かんちょうろう):池畔に建つ煎茶室で、「現存する日本最古の煎茶室」として知られています。中間階構造で、瀬戸内海の潮の満ち引きを眺めながら茶を楽しむ趣向があったとされます。また、舟付き場が設計されており、江戸時代には舟でこの茶室に赴くという趣向も残されています。
- 母屋・母屋建築群:庭園と一体的に機能する母屋・邸宅部構造があり、茶婚式(あとで触れます)などでも使われます。
- 社・百本鳥居:庭域内には稲荷社があり、真っ赤な鳥居連なり(百本鳥居)としてフォトスポットになっています。
- 石投げ地蔵尊:庭の一角に石投げ祈願の伝承をもつ地蔵尊があり、願い事を白い石に書いて台座に投げて乗れば成就するといわれる風習があります。江戸時代の洪水で一度池底に沈んだが、1983年に復元されたとの記録もあります。これらの構造物は、ただの飾りではなく、回遊体験や視線誘導、物語性(茶・信仰・願掛けなど)を付与する機能を持っています。
名称と意味づけ
庭園名「万象園」は、「森羅万象(しんらばんしょう)」、すなわち「この世に存在するすべてのもの」を包摂するという意味を込めています。近江八景をモデルとする島名、潮風を取り込む設計、茶や社を通じた精神的要素の導入など、庭園そのものを自然・水・建築・信仰が融け合う場とする意図が感じられます。
総じて、中津万象園は 水辺と橋、樹木、建築・茶室・信仰構造物 の多層的配置と調和を通じて、歩く者が時間と視線の変化を感じられるように設計された日本庭園の典型と、独自要素の複合を併せ持つ庭園です。

藩主別邸・茶遊び・風流の場
築庭初期には、藩主やその家族・家臣が庭を眺め、茶を楽しみ、海景を取り込みながら風流を味わう場として機能していたと考えられます。特に観潮楼のような茶室を通じて、庭を眺めながら茶をたしなむという嗜好性の高い用途が組み込まれていたことが伝えられます。また、庭全体を借景・風致景観の場とし、詩歌を詠む場、書斎的な役割を兼ねた別邸空間とする意図もあった可能性があります。
つまり、ただ「見せる庭」ではなく、屋内と屋外の往還、身体の動き、茶・風景との対話を含む総合的風景空間として設計されたと言えます。
明治以降:公共開放と観光化
藩制度の崩壊後、中津万象園は公・私の管理を経て、徐々に一般市民や来訪者に開かれる庭園となっていきます。
庭園を保存活用する動きにより、観光資源・文化資産としての役割が強まりました。
近年では「丸亀城天守との共通入園券」など、地域観光ルートとの連携が進められています。美術館併設:文化拠点としての役割
庭園内には 丸亀美術館 が併設されており、次のような展示施設が整っています。
- 絵画館:フランス・バルビゾン派(ミレー、コロー、クールベら)を中心とした洋画を収蔵・展示。
陶器館:イラン・イラク地域を中心とする彩文土器、陶器、ガラス器など、オリエント地域の考古資料を展示。
このように、園の風景資源とアート・歴史資料を併せて鑑賞できる複合的な空間として機能しています。
撮影ロケーション・婚礼・イベント利用
中津万象園は、その風景美を活かして 前撮り写真のロケーションとしても人気があります。また、敷地や母屋を使った式典、茶婚式(お茶を媒介とした儀式形式)といった婚礼プランも提供されており、「庭を舞台にした人間の営み」を具現化する用途となっています。
さらに、季節ごとのイベント(庭園ライトアップ、うちわづくり体験など)やガイドツアー、写真教室など多様な文化利用がなされています。最近では 丸亀うちわミュージアム が移転してくる動きもあり、それを含んだ体験系観光資源化の試みも始まっています(うちわづくり体験など)。
香川が誇るこの庭園で、二度とない最高の門出を彩ってみませんか。

きものサロン桂 貴迎館
〒760-0079 高松市松縄町1067-19
TEL 087-869-2255 営業時間 10:00~19:00
きものサロン桂 丸亀店
〒763-0055 丸亀市新田町150ゆめタウン1F
TEL 0877-58-2255 営業時間 10:00~19:00