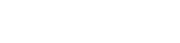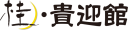【徹底解説】辻が花とは?
皆様こんにちは。貴迎館の武下です。
節目を彩る振袖には、由緒正しい華麗な模様があしらわれたものを選びたい。そのように考えられている方もいらっしゃることでしょう。しかし現代の振袖は多種多様であり、その取捨に頭を悩ませることも少なくないかと思います。
そこでおすすめしたいのが、「辻が花」と呼ばれる染物です。複数の手法を次々に使って手作業で仕上げられるこの逸品は、言うなれば超絶技巧の結晶。晴れの日を飾るにふさわしい存在です。日本の歴史においてごくわずかな期間に隆盛し、一度は途絶え、されど蘇った和の大輪。その歴史や魅力について解説いたします。
1.辻が花とは何か?

辻が花は、絞り染め(特に縫い締め絞り)を基本とし、さらに描き絵(墨描きや色挿し)、摺り箔、刺繍などを加えた装飾性の高い染織文様染です。
使用される生地は、絹(特に練貫・半練・白生地)、また夏用の帷子などが中心。麻地も用いられた例があります。
名前の由来には諸説ありますが、「辻」=十字形または街角や交差点の「辻」、あるいは模様に十字形の要素を持つもの、そこに花を配するという意匠的要素が一つの説として有力です。
2.由来と語義の変遷

中世(室町時代など)の史料をたどると、「辻が花(染)」という言葉は出てきますが、その時点で「縫い締め絞り」が必ずしも含まれていた、という記述は確認されていないという研究があります。
また、「辻が花(染)」とは、当初「女性・武家・公家の女性、あるいは元服前の男子が、帷子として着る衣服」であり、赤色が特徴の生絹あるいは麻地の衣であったとする説もあります。
その後衰退と消滅を経て、特に近代・戦後の染織史研究・古裂収集家・展覧会・呉服業界で、「縫い締め絞りを主体とし、描き絵・金彩等を加えた豪華な染織品」が「辻が花」と呼ばれることが一般化しました。
3.秘められた歴史

1. 室町時代
辻が花染はまだ明瞭な形態として確立していないものの、「帷子」「生絹」「赤色を用いた衣装」など、後の辻が花の要素と思われるものが登場します。 技法として、絞り・草木染・防染・描絵などの要素があった可能性が高く、後に発展する多色・装飾性の高い形態の前史と見なせます。
2. 安土桃山時代
辻が花染が発展し、最も豪華で装飾性の高い形で製作された時期です。絞りだけでなく、縫い締め絞り・描き模様・金銀箔や刺繍・色差しなどを加えた染織品が多く作られました。衣装としては小袖・胴服・裾絵羽などが代表的な例です。また、武将などの衣装としての使用や、公家・武家の儀礼や装飾目的の小袖にその威光があったことが、現存品からもわかります。
3. 江戸時代
江戸時代に入ると、友禅染などの型染・引き染め・摘み縫い絞りなど、比較的効率よくかつ多彩な表現ができる染織技術の開発・普及が進みました。同時に、辻が花のような手間が非常にかかる技法は姿を消していきました。また、「辻が花」の名称が俳諧や考証文学中で語られることはあっても、日常的な用語としては薄れていき、「模様染め」「絞り染め」等の総称の中に取り込まれていったとの指摘もあります。
4. 近現代の復興と再評価
明治以降、日本の古染織品の収集・美術館・展覧会活動が活発になり、辻が花の古裂(こぎれ)が注目され始めました。近代の研究者やコレクターが「辻が花」という語を整理し、技法的・意匠的な特徴をもとに定義を与えていきます。
戦後には「辻が花」復興を志す染色家・工房がいくつか現れ、古裂を手本としながら現代の素材・色彩感覚を取り入れた作品を制作。一部は芸術性・工芸性が非常に高く評価され、高級振袖や訪問着等の品として希少価値を持つようになったのです。
4.無二の技法と意匠

絞り染めの中心技
特に縫い締め絞り(生地を針と糸で縫い、その糸を強く引き締めて防染部分を作る)が主要な手法です。この他に、帽子絞り、筒絞り、桶絞りなど複数の絞り技法を用いて染め分けを行う例があります。
描き絵 / 墨描き /色挿し・暈し
絞り部分で模様の輪郭が白く残っている部分を活かす技法です。その上から濃淡の暈しを入れたり、墨で草花を描くなど絵画的な表現を加える傾向にあります。これにより静と動、光と影、あるいは余白と彩色の調和が生まれます。
加飾要素
金箔・銀箔・摺り箔、刺繍などを併用したものもあります。これらは特に豪華な振袖で見られ、素材・技術手間ともに特別感を演出する何よりの要素となっています。
図案・意匠の構成
草花文様(桜・藤・菊・梅など)、州浜形・松皮菱・石畳模様などの幾何学的・自然モチーフの融合、十字格子や散らし文(小花を散らす・文様を荒く散らす)などが特徴。配色は絞りで防染された白地を基調に、萌葱色・浅葱色・紅・紫などの彩が使われることが多い。生地地色・下染め・暈しとの兼ね合いが重要。
生地の種類
練貫絹、半練、絹白生地、単衣(裏無し)の夏衣としての帷子、麻素材などが挙げられます。生地の薄さ・張り・風合いが技法の出来を 左右するため、記事選びも重要な項目です。
5.その価値と希少性

1. 希少性
先にも述べたように、辻が花が盛んだったのは室町末期から江戸初期に限られています。ゆえに技法の継承が途絶えており、オリジナルの古裂が非常に少ないのです。時に「幻」とも称されるほど、非常に歴史的価値の高いものとなっています。状態の良いものや図案の整ったものとなるとさらに稀です。このような背景から、当時の辻が花に使われた技術はロストテクノロジーと呼んでも差し支えないでしょう。
2. 手間と技術
絞りや刺繍など複数の技法を高度に組み合わせるため、制作に要求される時間や練度は並外れたものとなっています。特にオリジナルの古裂においては全工程が手作業によって成り立っているため、殊更に職人の神技が光ります。
近現代の復元作品でも、その作家・工房の名声や技術力が価格に反映されます。この点については他の模様と同じです。
3. 歴史的・文化的価値
古来の武家や公家の衣装、陣羽織・胴服・小袖など美術史資料としてこの上ない有用性を秘めています。重要文化財に指定されている作品も複数あり、我が国の着物文化を紐解く貴重な財産です。
4. 装いとしての価値
振袖などの晴れ着、成人式・結婚式・舞台衣装など、フォーマル・記念の場で用いられることが多いです。「格式」「伝統」「華やかさ」の象徴として扱われています。
模様の散らし方や柄の流れ、色合いの調和が、着姿の印象や写真映えなどに強く影響します。そのため、作り手や選び手のセンスが一層重視される柄ともいえるでしょう。
6.現代における辻が花の立ち位置

復元・再現作品
多くの工房・作家が古裂を研究し、伝統技法を復元しています。こうした復元作品は、図案・色彩・技術の面で古来の雰囲気を出そうとするため、非常に手間がかけられています。振袖においては、高級感を醸し出す重要なエッセンスです。
「辻が花風」あるいは「辻が花型」
完全再現ではなく、絞り風・描絵風・彩色・装飾を取り入れて「辻が花」をイメージさせるデザインのものです。これらは価格を抑えつつも華やかさ・伝統感を出したい方に人気があります。
色・模様のトレンド
かつては古来の色(浅葱・萌葱・紺・紫・紅など)を用いたものが好まれていましたが、現代的な色彩・グラデーション・ぼかしを取り入れたものも増えてきています。模様の散らし方やアクセントの刺繍・箔使いなども、写真映えの観点から意識される部分です。
7.辻が花を選ぶ時には

きものサロン桂では、伝統と品質を重視した「本物の辻が花振袖」を揃えており、ご希望に応じて特別な一着をご紹介可能です。あなたの晴れの日を美麗な花で彩りましょう。
1. 歴史的/技法的知識に裏打ちされた品揃え
桂では、ただ華やかなデザインを揃えるだけでなく、辻が花の技法的要素をしっかり備えた振袖を取り扱っています。これにより、「漠然と辻が花がいい」という選択よりも、一歩踏み込んだ本物志向の一枚を選べます。
2. 購入・レンタル双方のオプション
購入をお考えの方には長く着られる一着としての価値を、レンタルをお考えの方にはコストパフォーマンスと安全さを両立できるプランを用意しています。振袖の保管・クリーニングなどのメンテナンスもサポート可能です。
3. コーディネートと小物選びのサポート
辻が花振袖は柄・色使いが豊かなので、帯・帯揚げ・帯締め・重ね衿・重ね襟など、小物との調和が非常に重要です。桂では着付けスタッフ経験豊かなコーディネーターが、小物合わせや撮影映えを踏まえてご提案いたします。
4. 個別対応と特別感
予算や好みを丁寧にお伺いし、仕立て替え・染め直し風のアレンジ・特注対応など可能な限りバックアップします。「人とかぶらない」「自分だけの一着感」を重視されるなら外せない選択肢です。桂の辻が花振袖は値段以上の手仕事・素材・見た目の重厚さを備えているものが多く、後から「この振袖を選んでよかった」と思える満足度が高いとご好評いただいています。

きものサロン桂 貴迎館
〒760-0079 高松市松縄町1067-19
TEL 087-869-2255 営業時間 10:00~19:00
きものサロン桂 丸亀店
〒763-0055 丸亀市新田町150ゆめタウン1F
TEL 0877-58-2255 営業時間 10:00~19:00